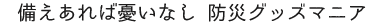地震について知っておこう

首都直下地震や南海トラフ地震など、日本では巨大地震の発生が予測されています。日本で地震が多い理由や地震の強さなどについて解説します。
日本で地震が多い理由
日本で地震が多い理由は日本周辺にはプレートと呼ばれる岩盤が存在するためです。地球の表面は十数枚のプレートに覆われています。プレートはそれぞれが別の方向に向かって、年間数cmの速さで動くため、プレートとプレートの間には常に圧力がかかっている状態です。その圧力が限界に達し、プレート間が壊れると地震が発生します。日本は4つのプレートに囲まれているため、世界有数の地震発生地域となっているわけです。今後もさまざまな地震が発生すると予測されていて、政府も今後、30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を公表しています。
マグニチュードと震度の違い
マグニチュードは地震本体の大きさを表し、震度は揺れの強さを表します。電球で例えるとマグニチュードと震度は、ワット数と明るさに相当します。100ワットの電球でも近ければ明るく、遠ければ暗くなります。ワット数はひとつの値ですが、明るさは場所によって感じ方が違うようにたくさんの値があります。地震だとマグニチュードはひとつの値で、震度は各地によって異なるわけです。マグニチュード9.0の地震の場合、震源の近くは震度が7になるのに対して、遠く離れた場所だと震度0になります。
長周期地震動とは
地震による揺れは地面を伝わっていくうちにだんだん弱くなっていくのが普通です。しかし、長周期地震動のようなゆっくりした揺れは弱まり方が穏やかという特徴があります。そのため、長周期地震動は遠くまで強い揺れが伝わることが多く、多くの被害を及ぼしました。
余震はどうして起こる?
最初の大きな地震を本震、その後に起こる地震が余震です。巨大な地震が起こると、揺れは1度きりではなく複数回余震が起こるとされています。圧力でプレートが壊れ地震になると説明しましたが、本震の発生である程度、プレートの圧力は解消されます。しかし、周辺の活断層はゆがんだままです。その周辺の活断層を元に戻そうと余震が発生するとされています。余震の発生確率は定かではなく、活断層の長さで変わり、断層が長く続いていると遠方でも余震が発生する可能性があるので注意が必要です。
本震によって建物に異常をきたした場合や津波、土砂災害などが発生していた場合、余震によってさらに被害が拡大する恐れがあります。余震は1週間ほど続くとされているため、二次災害を防ぐためにも、そのような場所には近づかないようにしましょう。