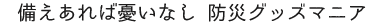被災によってローンの返済が困難になってしまったら
自然災害は、私たちの日常生活に大きな影響を与えることがあります。命が助かっても、住まいや仕事場が被害を受け、住宅ローンや事業ローンといった負債の返済が困難になるケースも珍しくありません。そのような状況に直面したとき、「破産」などの法的手続き以外の選択肢として利用できるのが「自然災害債務整理ガイドライン」です。このガイドラインは、生活や事業の再建を支援するために設けられた民間のルールであり、経済的な立ち直りを支える大きな助けとなります。
自然災害債務整理ガイドラインとは?
自然災害債務整理ガイドラインとは、自然災害によって住宅や事業所などに大きな被害を受け、ローン返済が困難になった個人または個人事業者が、破産などの法的手続きに頼らずに債務整理を行える仕組みです。銀行などの金融機関と話し合い、債務の減額や免除を受けることを目的としています。このガイドラインは2015年に策定され、2016年4月から適用が開始されました。
ガイドラインの利用対象者
このガイドラインを利用できるのは、以下の条件を満たす個人または個人事業者です。
- 災害救助法が適用された自然災害の被災者
東日本大震災やそれ以降の大規模な自然災害で、災害救助法が適用された地域で被害を受けた人が対象です。 - 既存のローン返済が困難になった場合
自然災害の影響で、住宅ローンや事業ローン、自動車ローンなどの返済が難しくなった、または近い将来返済ができなくなる可能性が高い場合に適用されます。 - その他の要件を満たすこと
例えば、災害発生前に期限を守った返済を行っていたこと、また債務整理を行うことで債権者が経済的に合理的な回収を見込めることなどが必要です。
ガイドラインのメリット
自然災害債務整理ガイドラインを利用することで、被災者は以下のようなメリットを享受できます。
個人信用情報への登録が回避される
破産手続や再生手続では、これらの情報が個人信用情報として登録され、新たな借入れやクレジットカードの発行に制限が生じます。一方、ガイドラインに基づく債務整理では、信用情報への登録が行われないため、その後の資金調達に影響を与えません。
弁護士などの登録支援専門家による無料サポート
債務整理をスムーズに進めるため、弁護士や税理士、公認会計士などが登録支援専門家として支援を提供します。このサポートは無料で受けられるため、経済的負担を軽減できます。
一部の財産を手元に残せる
預貯金などの一部の財産を「自由財産」として保持することが可能です。被災者が生活を再建するための資金を一定程度確保できるよう配慮されています。
ガイドラインを利用する手続きの流れ
ガイドラインによる債務整理は、以下のステップで進められます。
- 金融機関への申し出
最も多額のローンを借りている金融機関に、手続きを開始したい旨を伝えます。申し出の際には、借入状況や年収、資産などの情報を整理しておくとスムーズです。 - 登録支援専門家への依頼
金融機関の同意が得られたら、地元の弁護士会などを通じて登録支援専門家を手配します。この専門家が中立の立場で債務整理をサポートします。 - 債務整理の申し出
登録支援専門家の助けを借りて、申出書や財産目録を作成し、全ての金融機関に債務整理を申請します。この段階で返済や督促は一時停止となります。 - 調停条項案の作成
債務の免除や減額を盛り込んだ調停条項案を作成します。 - 特定調停の申立
金融機関の同意を得た後、簡易裁判所に特定調停を申し立てます。この際、債務者自身が調停に出席する必要があります。 - 調停条項の確定
特定調停手続を経て調停条項が確定すれば、債務整理が成立します。
新型コロナウイルス感染症への特則
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた個人や事業者も、このガイドラインの特則を利用できます。この特則は、感染症の影響で収入が減少した人が、破産などの法的整理を避け、生活や事業の再建を図るために設けられたものです。
債務整理を検討する際の注意点
ガイドラインを利用した債務整理は、債務者と債権者の合意が前提となります。また、一定の返済義務が残る場合もあるため、専門家の意見をしっかり聞いて手続きを進めることが重要です。
最後に
自然災害による被災は、予期せぬ形で私たちの生活に打撃を与えます。しかし、適切な制度や支援を活用することで、生活や事業を再建する道が開かれます。「自然災害債務整理ガイドライン」はその一助となる制度です。被災後にローンの返済が困難になった場合は、一人で悩まず、専門機関に相談してみましょう。